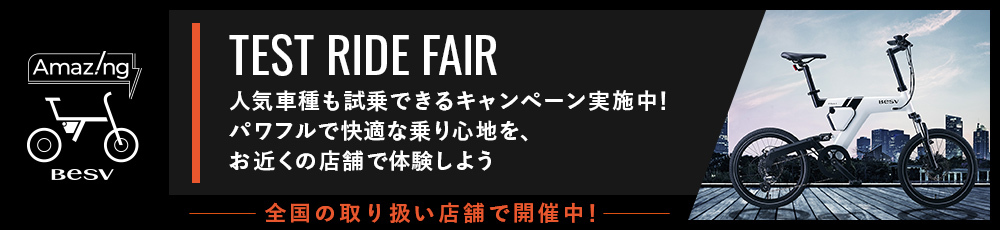毎日の通勤や買い物に欠かせない電動アシスト自転車。その性能を左右する重要な部品であるバッテリーは、決して安くはない買い物です。しかし、適切な使い方とメンテナンス方法を知っておけば、バッテリーの寿命を大幅に延ばすことができます。プロが教える具体的なケア方法と、知っておくべき交換のタイミングについて、詳しく解説していきます。
電動アシスト自転車のバッテリー交換の目安と費用
電動アシスト自転車の走行距離や、重量、取り回しの良さなど、機能性/利便性に関する重要な部品であるバッテリー。日常生活に欠かせない電動アシスト自転車のバッテリーが劣化してきた場合、どのタイミングで交換すべきなのか、またその費用はどのくらいかかるのか、多くの方が不安を感じています。ここでは、バッテリー交換に関する具体的な判断基準や費用について、詳しく解説していきます。
バッテリーの寿命と交換時期の判断方法
電動アシスト自転車のバッテリーの寿命は、使用頻度や使用環境によって大きく異なります。一般的な期間の目安として、標準的な使用で4〜5年といわれています。自転車本体の製品寿命がおおよそ10年とすると、購入した電動アシスト自転車を使い続ける中で、1度はバッテリー交換する機会が訪れると考えられます。また、最近のリチウムイオンバッテリーは繰り返しの継ぎ足し充電が可能であり、その充放電回数では700〜1000回程度が寿命の目安とされています。しかし、これはあくまでも平均的な数値であり、実際の寿命は使い方によって変動します。
なお、この充放電回数とは、充電器を挿した回数のことではありません。最近のリチウムイオンバッテリーには、バッテリーマネジメントシステム(BMS)が内蔵されており、バッテリーの充電容量が0%→100%分まで充電されて初めて1サイクルとカウントします。つまり、毎日20%分ずつを充電したとして、5日間、毎日充電を行って初めて、20%×5回=100%で1サイクル(1回)分としてカウントをします。一般な使用環境(適正温度や湿度)において、このカウントが500回ほどで新品時の約70%~80%程度に容量が劣化するといわれています。この継ぎ足し充電を頻度高く実施することで、バッテリーの劣化を著しく加速することはありませんので、こまめに充電を実施しても問題はありません。
BESV製バッテリーの場合は、300サイクル:80%、500サイクル:70%、700サイクル:65%、1000サイクル:45%を標準としています。
バッテリーの交換時期を判断する具体的なサインとしては、以下のような症状が挙げられます。まず、フル充電しても以前より走行距離が明らかに短くなってきた場合です。
1回の充電で必要な距離を走れなくなったと感じたり、今まで以上に必要な充電頻度が増える、日常的に不便を感る、などがあれば交換を検討するタイミングといえます。
また、走行中にバッテリー残量表示に余裕があるのに、突然アシストが切れるなどの症状が出た場合も、バッテリーが劣化している可能性があるので、販売店での点検等を行うことが必要になるでしょう。
また、バッテリーの外観にも注目する必要があります。膨らみやひび割れ、異常な高温化などが見られる場合は、安全面を考慮し、速やかに使用を停止し、販売店に相談をしましょう。
バッテリー交換にかかる費用の相場
バッテリー交換の費用は、メーカーや容量によって大きく異なります。一般的な相場として、メーカー純正品の場合は4万円から8万円程度が目安となります。この価格差は主にバッテリー容量の違いによるもので、大容量モデルほど高額になる傾向があります。
また、バッテリー容量の大小は、Ah表示のみならず、V(ボルト)数にも着目しましょう。
例えば、日本製の電動アシスト自転車は24Vのものが主流であり、海外製を中心としたスポーティな電動アシスト自転車の場合は、36Vが主流です。これは、電圧の差によるもので、V数が大きいほど、瞬間的な電気出力が高く、登坂時の加速などにも有効です。
具体的には、12Ah×24Vのバッテリーと、8Ah×36Vのバッテリーを比較した場合、どちらも288Whとなり、実容量は同サイズとなります。よって、バッテリーの容量比較をする場合は、Whで比べるようにしましょう。
バッテリーは、ECサイトなどでも購入することができますが、個人売買や中古品、互換性バッテリーなどは、あまりお勧めできません。高額であってもメーカー純正品の新品を、販売店や公式サイトで購入するようにしましょう。正規品の新品購入であれば、バッテリー単体へのメーカー保証が付帯する場合がありますので、買い替え後の製品保障の有無についても事前に調べておくとよいでしょう。
BESVのバッテリーは、7Ah×36V=252Whタイプで43,780円、10.5Ah×36V=378Whタイプで、49,940円、最も高額なモデルは17.5Ah×36V=630Whで85,800円です。
※2025年3月時点、価格は税込。
電動アシスト自転車のバッテリー性能を長持ちさせるコツ
電動アシスト自転車のバッテリーは、構成パーツの中でも最も高額なパーツの一つです。
できるだけ長く性能を維持し、バッテリーを長持ちさせることは、経済的にも環境的にも重要です。日々の適切な使用方法とメンテナンスを心がけることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。ここでは、バッテリーを長く使い続けるための具体的なポイントについて解説していきます。
正しい充電方法と保管のポイント
バッテリーの寿命を最大限延ばすためには、適切な充電方法と保管方法で、ご利用いただくことが極めて重要です。リチウムイオンバッテリーは、充電方法や保管状態によって性能が大きく左右されます。まず、充電に関する基本的なルールとして、使用後はなるべく早めに充電を行うことをお勧めします。バッテリー残量が20%を下回った状態での放置は、バッテリーの劣化を早める原因となります。
また、充電時は直射日光を避け、風通しの良い場所で室温(10-25度程度)での充電を心がけましょう。特に真夏や真冬など、極端な温度環境下での充電を避けることが重要です。
長期間、バッテリーを放置することで自然放電による残量の低下や、それによって完全放電状態になる場合があります。一度完全放電状態になると、それを復旧させることは困難です。また、バッテリー残量が極めて少ない状態から、さらに継続的に自然放電が進行した場合、過放電状態となり、発煙・発火リスクが上昇します。上記の理由から、保管時の充電容量にも注意をしましょう。長期間、使用予定がない場合などは、30-90%程度の充電状態で保管をするのが理想的です。
とはいえ、充電器を差しっぱなしで保管することも望ましくありません。一般的な充電器は、満充電になれば、充電は停止されますが、バッテリーに充電器を装着したまま長期間放置していると、自然放電によってバッテリー残量が減った都度、充電が再開され、それが繰り返されます。常時100%の満充電状態を維持することも避けるべきです。よって長期間保管時は、一度90%程度まで充電を行い、その時点で充電器を取り外して保管をするのがよいでしょう。
その後も、半年に一回程度の充電を行い、バッテリーの完全放電を防ぐことが大切です。保管場所は湿気の少ない冷暗所が適しており、直射日光の当たる場所や高温多湿の環境は避けるべきです。
BESV製品の場合は、バッテリーの事故リスクを回避するための安全機能がプログラムされています。一定の基準以上に放電が進行すると、「過放電防止機能」が働きバッテリーをロックし、強制的に利用停止状態とすることで、完全放電を防止し発煙や発火などの事故リスクを回避します。ただし、この利用停止状態になると、バッテリーの復旧もできなくなります。
なお、BESVの最新の充電器ではスマートチャージングシステムを採用しています。急激な充電によってバッテリーを損傷しないように、容量が少ない状態から80%容量まではスピーディに、その後80%から100%までの充電を緩やかに行うことで、バッテリーに付加を与えず、より長持ちさせる工夫をしています。
日常的なメンテナンス方法
バッテリーの性能を維持するためには、日常的なメンテナンスも欠かせません。特に重要なのが、バッテリーの接点端子部分の清掃です。接点部分に埃や汚れが付着すると、充電効率の低下や接触不良の原因となります。乾いた布等で定期的に軽く拭き取るだけでも、トラブルの予防につながります。
また、バッテリーの装着部分や自転車本体との接続部分のパーツやケーブル類にも注意を払う必要があります。がたつきやズレがないか定期的にチェックし、必要に応じて調整や清掃を行います。雨天走行後は特に念入りな点検が重要で、水分が残らないように丁寧に拭き取ることをお勧めします。多くのバッテリーは、IPX4~IPX6などの防水基準をクリアしたものがほとんどですが、完全防水ではないので、水没や浸水には注意をしてください。
充電器についても定期的な点検が必要です。コードの損傷や端子部分の変形などがないか確認し、異常が見られた場合は使用を中止して専門店に相談しましょう。
また、充電時において、充電器やバッテリーが熱を持つことがあります。置き式充電器に比べて、挿し込み式の充電器や小型充電器の場合は、筐体自体がコンパクトなため、温度をより感じやすくなることがあります。取扱説明書に、最大許容温度などの記載があることを確認しましょう。
バッテリー端子部分に汚れが付着していると通信エラーを起こし、W01/E04といったエラー表示が発生する場合があります。バッテリー端子には、通電を行うプラス端子・マイナス端子の他、バッテリーの残量や充放電回数、エラー履歴などのデータの受送信を行う通信端子も存在します。いずれの端子も、ほこりや汚れの付着はエラー発生の原因になります。
また、BESVの充電器は軽量・小型に設計されており、筐体自体のサイズが小さい為に、充電時の温度上昇を感じやすくなっています。ただし、安全装置として、バッテリー・充電器双方に、温度センサーが内蔵されている為、一定の温度以上になると、充電を一時停止する安全機能が内蔵されています。
基本的な推奨室温は-10℃~45℃の環境下での充放電を想定しています。それ以上/以下となると、プロテクションが働き充放電を一時停止させます。また、充電時の充電器の許容温度は+40℃まで熱くなる可能性がありますが、一定の温度(最大70℃)になると充電を停止します。手で持った時に温度を感じることがありますが、許容範囲内の温度であれば問題はありません。
気をつけるべき使用上の注意点
バッテリーの寿命を縮める原因の多くは、不適切な使用方法にあります。落下や水没などはもちろん、気温の影響も見逃せません。夏場における車内/トランクでのバッテリーの保管や、炎天下での駐輪、厳冬期の屋外保管は避けるべきです。極端な温度環境下では、バッテリーの性能が一時的に低下するだけでなく、恒久的な劣化を引き起こす可能性があります。可能な限り、適温環境での使用と保管を心がけましょう。
防水性にも注意が必要です。電動アシスト自転車は一定の防水性能を備えていますが、バッテリー部分は完全防水ではありません。大雨や洗車時の直接的な水かけは避け、万が一水濡れした場合は速やかに水分を拭き取り、十分に乾燥させてから使用することが重要です。特に高圧洗浄機による洗車は絶対に行ってはいけません。
万が一、バッテリーに異常を感じた場合は、速やかに利用を停止し、販売店にご相談ください。また、リチウムイオンバッテリーは、リサイクルすることが義務付けられています。不適切な処分は事故につながる可能性があるため、注意が必要です。バッテリーの廃棄方法は、リサイクル協力店や購入店舗に持ち込む、自治体の粗大ゴミとして処分するなどがありますが、メーカーによっては、上記方法では対応できない場合がありますので、販売店やメーカーに確認をしてください。
BESVでは、不要なバッテリーは、専門のリサイクル事業者にて、リサイクル処理をしています。販売店経由で、弊社まで処分をご依頼ください。
(2025/2時点、BESVは、小型充電式電池の再資源化に取り組む「一般社団法人JBRC」への加入準備を進めております。この手続きが完了すると、リサイクル協力店や自治体での回収受付が可能となります。
電動アシスト自転車選びで失敗しないためのポイント
電動アシスト自転車のバッテリー選びは、日常生活の快適さに直結する重要な判断材料です。特に交換や新規購入の際には、価格だけでなく、様々な要素を総合的に判断する必要があります。ここでは、バッテリー選びの際に押さえておくべき重要なポイントについて、詳しく解説していきます。
安全なバッテリーかどうか(PSEマーク)
PSEマークとは、電気用品安全法に基づいて電気製品に表示されるマークで、「Product+Safety+Electrical appliance & materials」の略です。電気用品が安全基準を満たしていることを示しています。日本国内では、電動アシスト自転車はもちろん、テレビ・冷蔵庫や電気カーペット、モバイルバッテリーに至るまで、電化製品を輸入・販売するには、このPSEマークの表示と輸入事業者名の併記が法律によって義務付けられており、違反時には懲役刑や罰金刑が科される、非常に重要かつ必須の判断ポイントです。
電動アシスト自転車においては、バッテリーと充電器が、この対象となり、バッテリーには、丸型PSEマーク(特定電気用品以外)、充電器にはひし形PSEマーク(特定電気用品)の表示と併せて輸入事業者名がマークの至近に記載される必要があります。お買い上げ時には、バッテリーと充電器に、このPSEマークの表示と輸入事業者名の表示があるかを、きちんと確認しましょう。
特定電気用品
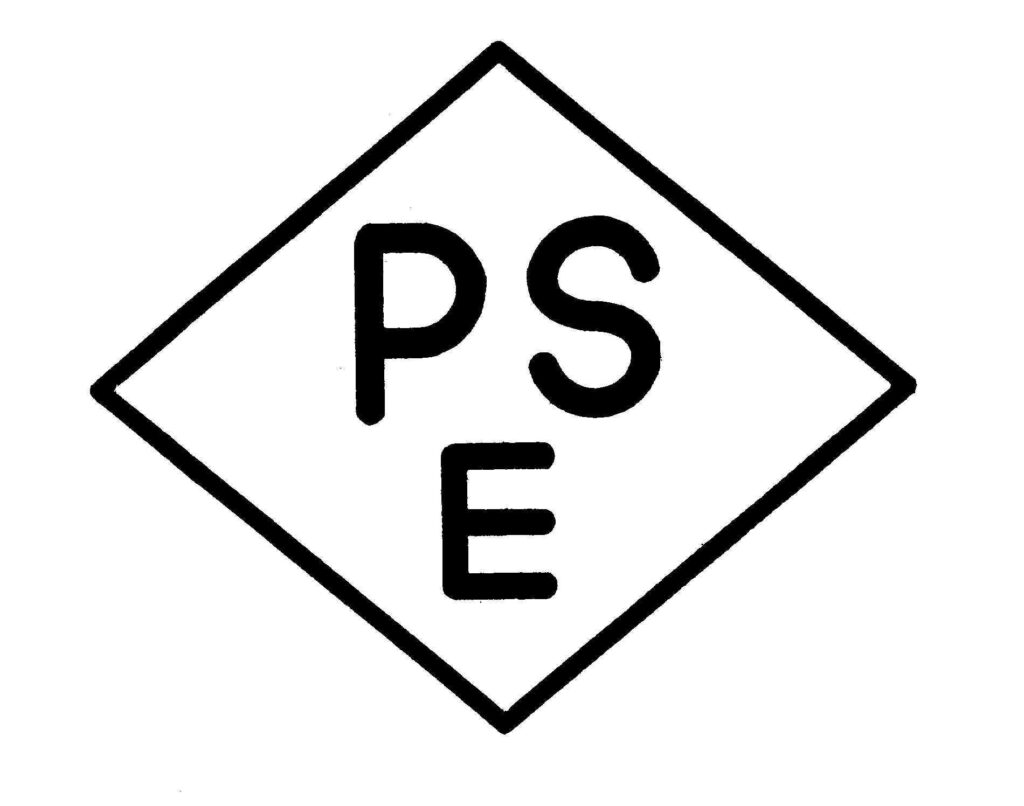
特定電気用品以外の電気用品
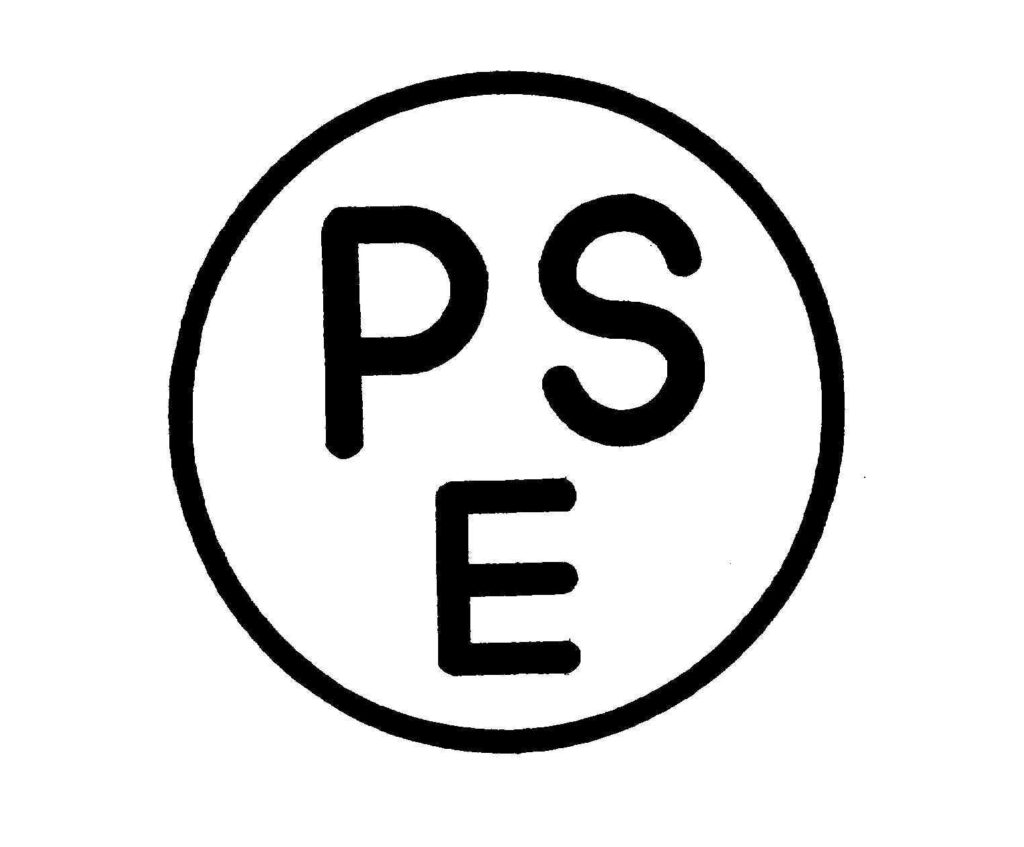
参考:電気用品安全法の概要 – 電気用品安全法(METI/経済産業省)
容量・充電時間・走行距離の見方
バッテリーの性能を判断する上で重要な指標の容量は、以下の3つの数字から判断します。
・Ah:時間あたりの電流の量(バッテリーの「持続時間」)
・V:電圧(バッテリーが提供する「力」)
・Wh:エネルギー量(バッテリーが供給できる総エネルギー)
この3つを組み合わせることで、バッテリーの容量や走行可能距離などを判断します。
Ah表示とV表示容量が大きいほど一回の充電での走行距離が長くなります。ただし、容量が大きいほど重量も増加し、価格も高くなる傾向があります。
カタログ等に記載の走行距離は、一般的にはJIS規格の測定方法に則って計測されますが、業界全体でその方法や測定条件が統一されているとは言い難いのが現状の為、あくまで目安となります。実際のご利用に際しては、カタログ記載距離の7割~8割程度になると考えられています。
また、実際の走行距離は、バッテリー容量だけでなく、使用条件によっても大きく変わります。坂道の多い地域や重い荷物を積載する場合、チャイルドシート装着の有無や、信号の多少、重いギアの多用や、低速走行の有無、空気圧管理など、実際の走行可能距離はご利用環境や車体の状態、使用方法によって、大きく異なることを念頭に置く必要があります。
充電時間についても、購入前に確認しておくべき重要なポイントです。一般的な充電時間は空の状態から満充電まで4〜5時間程度ですが、急速充電対応のモデルでは約2時間で80%程度まで充電できるものもあります。自分の生活パターンに合わせて、適切な充電時間のモデルを選択することが重要です。
バッテリーの保証とアフターサービスについて
バッテリーは電動アシスト自転車の中で最も高価なパーツの一つであり、保証内容とアフターサービスは購入判断の重要な要素となります。一般的な純正バッテリーの保証期間は2年程度ですが、メーカーによって保証内容や期間に違いがあります。
特に注目すべき点は、保証期間内であっても使用による経年劣化は保証対象外となることです。また、保証適用の条件として、定期的なメンテナンスや点検が必要なケースもあります。購入時には、これらの条件を詳しく確認しておくことをお勧めします。
アフターサービスについては、修理や交換の際の対応時間、代替バッテリーの貸し出しサービスの有無なども確認しておくと安心です。また、将来的なバッテリー交換の際の価格や、廃版予定の有無、互換性バッテリーの有無、その時点での在庫状況についても事前に確認しておくことをお勧めします。
まとめ
電動アシスト自転車のバッテリーは、日常的な使用における重要な要素です。適切な交換時期の判断、日常的なメンテナンス、保証の有無や、法令に適した安全性の保有、アフターパーツの入手の容易さ、価格など、ここまで解説してきた様々なポイントを参考にしていただければと思います。
特に重要なのは、バッテリーは単なる消耗品ではなく、電動アシスト自転車の性能を左右する重要なパーツだということです。初期費用は決して安くありませんが、適切な選択と日常的なケアを行うことで、長期的には大きな価値を生み出すことができます。
また、環境への配慮という観点からも、バッテリーの寿命を最大限延ばすことは重要です。正しい知識と適切な使用方法で、安全で快適な電動アシスト自転車ライフを楽しんでいただければと思います。
最後に
いま、BESVでは「TEST RIDE キャンペーン」を開催中です!
TEST RIDE キャンペーン
乗って試して、体験しよう。BESVが誇る、パワフルで滑らかな「スマートアシストモード」を実際に試すことができるTEST RIDEキャンペーン。
2025年、BESVでは全国の取扱店様にて、さらによりたくさんの試乗車をご用意し、実際の乗り味を体験頂けるキャンペーンを実施中です。
BESVのベストセラーシリーズのPSシリーズや優れたデザイン性を誇るVotaniシリーズ、AI搭載のSMALOなどたくさんの試乗車をご用意しております。
ぜひ、お近くの取扱店にて、BESVのアシスト性能を体験してください。