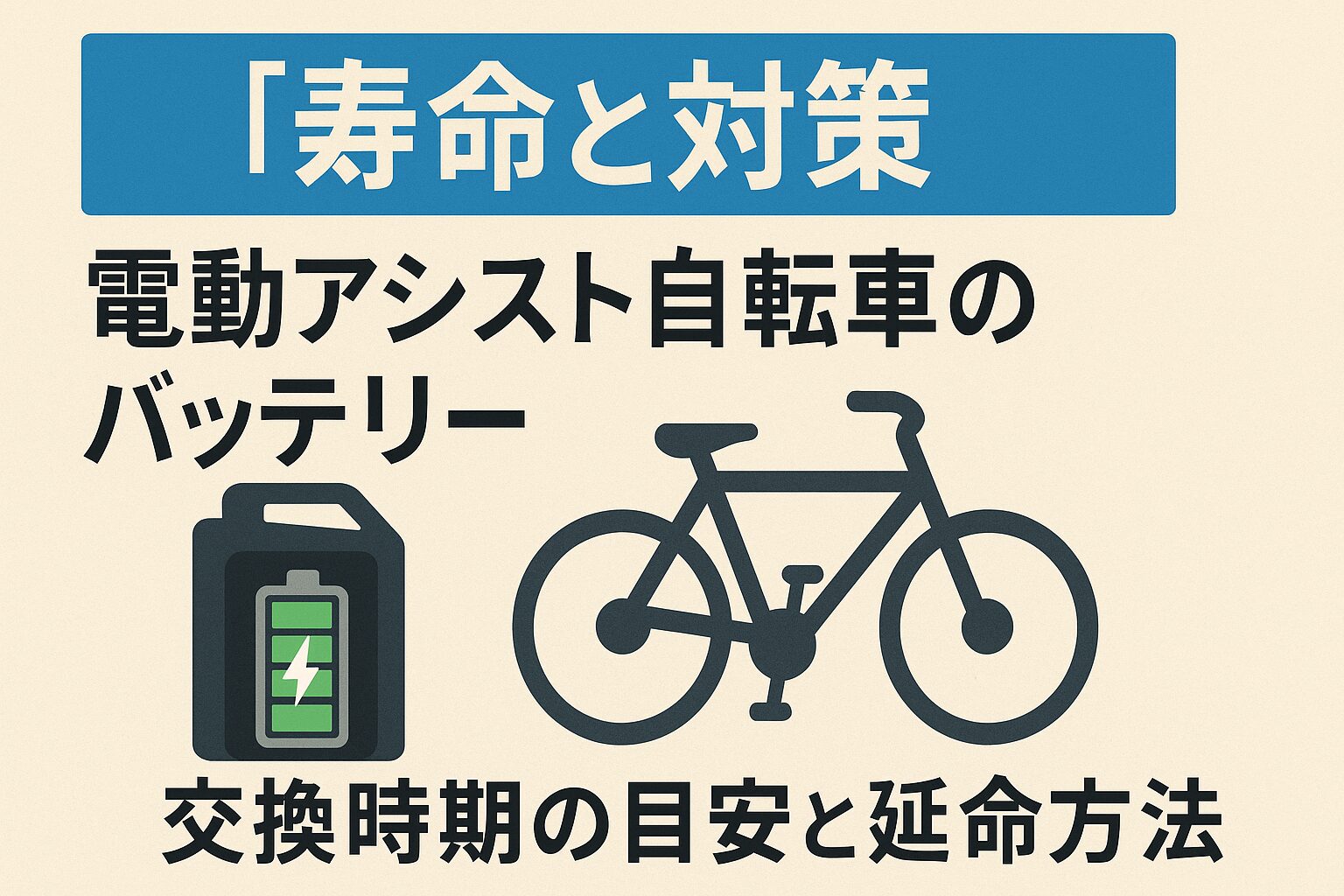電動アシスト自転車に乗っていると、ある日突然「あれ?以前より坂道がきつく感じる…」「満充電したはずなのに、すぐにバッテリーが減ってしまう…」と感じることはありませんか?これらは、バッテリーの寿命が近づいている兆候かもしれません。電動アシスト自転車の心臓部とも言えるバッテリーは、使用年数や充放電の回数によって徐々に劣化していきます。しかし、「いつ交換すべきなのか」「どうすれば長持ちさせられるのか」という疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、電動アシスト自転車のバッテリー寿命の目安や交換時期の判断方法、そして寿命を延ばすための実践的なアドバイスをご紹介します。これからお伝えする知識で、大切な愛車をより長く、経済的に使い続けるお手伝いができれば幸いです。
1. 電動アシスト自転車のバッテリー寿命はどのくらい?
電動アシスト自転車を快適に使用する上で、最も気になるのがバッテリーの寿命でしょう。通勤や買い物など日常的に使用していると、徐々にバッテリーの持ちが悪くなってくることを実感する方も多いはずです。実際のところ、電動アシスト自転車のバッテリー寿命はどれくらいなのでしょうか。
1-1. 一般的なバッテリー寿命の目安
電動アシスト自転車のバッテリーは、一般的に約2〜5年程度の寿命があると言われています。ただし、これは平均的な使用頻度(週に3〜4回程度、1回の走行距離が10km前後)を想定した場合の目安です。毎日長距離を走行する場合はこれより短くなることもあります。
バッテリー寿命を年数だけでなく充放電回数で見ると、リチウムイオンバッテリーの場合、フル充電・放電のサイクルで約500〜800回程度が一般的な寿命とされています。つまり、毎日使用して毎日充電する場合、理論上は約1.5〜2年で寿命を迎えることになりますが、実際には完全に放電することはまれなため、多くの場合でこれより長い期間使用できます。
また、現在主流のリチウムイオンバッテリーは、使い始めの容量を100%とすると、寿命とされる時点では約60〜70%まで容量が低下している状態を指します。つまり、完全に使えなくなるわけではなく、走行できる距離が新品時の6〜7割程度になった状態が「寿命」と考えられています。
1-2. バッテリー種類別の寿命の違い
バッテリーの寿命は、メーカーや種類によっても大きく異なります。一般的に大手メーカーの純正バッテリーは品質管理が厳しく、寿命も比較的長いとされています。
また、バッテリーの種類による違いも無視できません。現在の電動アシスト自転車では主にリチウムイオンバッテリーが使用されていますが、過去にはニッケル水素バッテリーなども使用されていました。リチウムイオンバッテリーは、ニッケル水素バッテリーと比較して軽量で容量が大きく、メモリー効果(完全に放電せずに充電を繰り返すと使用可能容量が減少する現象)も少ないという特徴があります。
さらに同じリチウムイオンバッテリーでも、容量(Ah:アンペアアワー)が大きいものほど、一般的に走行距離が長く、必要な充電回数も少なくて済みます。たとえば、8Ahと12Ahのバッテリーを比較すると、同じ距離を走るなら12Ahのバッテリーの方が充放電サイクルが少なくて済むため、理論上は寿命が長くなります。
1-3. 充放電回数とバッテリー寿命の関係
バッテリーの寿命を考える上で重要なのが「充放電回数」と「使用期間」です。リチウムイオンバッテリーは充放電を繰り返すごとに少しずつ劣化していきます(化学反応の繰り返し劣化)。また、単純な時間経過によっても、劣化は進行します(化学物質の自然分解)。
充放電回数の影響としては、充放電1回あたりの劣化度合いは、充電時の環境や放電の深さによって変わります。例えば、バッテリー残量が80%から100%までの充電よりも、0%から100%までフル充電する方が、バッテリーへの負担は大きくなります。したがって、毎回バッテリーを使い切ってから充電するよりも、残量が30%程度になったら充電するという使い方の方がバッテリーには優しいと言えます。ただし、使用頻度が少ないからといって安心はできません。バッテリー容量が100%に近い状態や、0%に近い状態で長期間放置するのは、どちらも劣化の原因になります。未使用の期間でも、時間の経過とともにバッテリー内部では化学的変化が進み、劣化は確実に進行します。特にセルバランスの乱れは、使用していなくても起こり得る問題のひとつです。最近の充電器の中には、充電時に自動的にセルバランスを補正する機能を備えたものもあります。そのため、たとえ少量でもこまめな充電を行うことは、放置よりもバッテリー寿命を延ばすうえで効果的といえます。
また、高温環境下での充電もバッテリーの劣化を早める要因です。夏場の車内や直射日光の当たる場所に自転車を置いた後すぐに充電すると、バッテリー内部の温度が上昇し、化学反応が活発になりすぎて劣化が促進されます。充電は常温環境(10〜30℃程度)で行うことが理想的です。
これらの条件を考慮すると、同じ電動アシスト自転車を使用していても、使用環境や充電習慣によって、バッテリー寿命は大きく異なることがわかります。適切な使用方法を心がけることで、バッテリーの寿命を最大限に延ばすことが可能なのです。
2. バッテリー寿命を判断する5つのサイン
電動アシスト自転車のバッテリーは徐々に劣化していくため、ある日突然使えなくなるというよりは、少しずつ性能が低下していきます。しかし、日常的に使用していると、その変化に気づきにくいこともあります。ここでは、バッテリーが寿命に近づいていることを示す5つのサインについて詳しく解説します。
2-1. 走行距離の明らかな低下
バッテリー寿命を判断する最も明確なサインは、一回の充電で走行できる距離の低下です。新品時と比べて走行距離が70%以下になったと感じたら、バッテリーの交換時期が近づいていると考えられます。
例えば、新品時には一回の充電で30kmほど走行できていたのに、同じ道のりを走っても20km程度しか走れなくなった場合は、バッテリーの容量が明らかに低下しています。ただし、冬季は低温によるバッテリー性能の一時的な低下もあるため、季節による変動も考慮する必要があります。
走行距離の低下を正確に把握するには、定期的に同じルートを走行して、どれくらいバッテリーを消費するかを記録しておくと良いでしょう。
2-2. 走行中の残量表示の変化
使用中にバッテリーの残量表示が急に減少する場合、内部の電圧やセルバランスが一時的に不安定になっている可能性があります。そのようなときは、一度満充電(100%まで)することで、正確さが戻ることがあります。ただし、この現象が頻繁に起こるようであれば、バッテリーの劣化が進行しているサインです。特に、内部のセル間の電圧差が広がっていると、正確な残量表示が難しくなり、電圧急降下のような症状が起きやすくなります。
その理由は、劣化したバッテリーは内部抵抗が高くなり、電圧が急に下がりやすくなり、急加速や、登坂時などの電圧の変化によって、残量表示が減少したり、アシストレベルが弱くなる場合があります。また、セルバランスが崩れていると、一部のセルが先に低電圧に達し、全体としての残量が“急に減ったように見える”ことで、残量表示が少なく表示されます。
2-3. 充電時間の変化
バッテリーの充電時間も寿命を判断する重要な指標です。劣化したバッテリーには以下のような特徴が見られます。
1. 充電時間が異常に短くなる
通常、空の状態から満充電まで約4時間かかっていたのに、最近は2時間ほどで充電が完了するようになった──このようなケースでは、バッテリーが劣化し、蓄えられる容量(Ah)が減っている可能性があります。
つまり、「満タン」になったように見えても、実際は“少ない電気しか入らない状態”になっているのです。
2. 充電時間が異常に長くなる
一方で、充電に以前より時間がかかるようになった場合も注意が必要です。これは、バッテリー内部の抵抗が増え、充電効率が落ちているサインと考えられます。
劣化が進むと、電気の流れがスムーズでなくなり、充電器が慎重に充電するため、時間がかかるようになります。場合によっては、充電が途中で止まったり、満充電にならなかったりすることもあります。
3. 充電中に異常発熱する
充電中のリチウムイオンバッテリーは、ある程度、温度は高くなります。
それが、手で触って明らかに熱いと感じる場合、内部抵抗の増加やセルの劣化によって過剰な発熱が生じている可能性があります。
この状態を放置すると、発煙・発火など安全リスクにもつながりかねません。発熱の症状が見られたら、速やかに使用を中止し、バッテリーの交換や点検を検討してください。
2-4. アシスト力の弱まり
電動アシスト自転車の特徴である「アシスト力」の低下も、バッテリー寿命の指標となります。坂道や重い荷物を載せての走行時に、以前よりもペダルが重く感じるようになった場合は、バッテリーが十分な電力を供給できなくなっている可能性があります。(空気圧が少ない、ブレーキの干渉、など他の原因が無い場合)
特に、満充電直後はまだアシスト力が維持されているものの、走行中に急激にアシスト力が低下する場合は、バッテリーの電圧維持能力が低下している証拠です。これは、バッテリーセルの一部が劣化して、全体の性能を引き下げている状態と考えられます。
また、アシストモードを高く設定しているにもかかわらず、低いモードと変わらないアシスト感になっている場合も、バッテリーからモーターへの電力供給が不十分になっている兆候です。
2-5. バッテリー本体の膨張や変形
リチウムイオンバッテリーの寿命末期には、物理的な変化が現れることもあります。バッテリーケースが膨らんでいたり、変形していたりする場合は、内部で化学反応が進みガスが発生している可能性があります。これは非常に危険な状態であり、直ちに使用を中止してプロに相談する必要があります。
また、バッテリー表面に亀裂が入っていたり、液漏れの形跡があったりする場合も、使用を中止すべき状態です。バッテリー内部の電解質が漏れ出すことは、発火や爆発のリスクを高めます。
2-6. 充電器のランプ表示の異常
多くの電動アシスト自転車の充電器には、充電状態を示すLEDランプが付いています。このランプの挙動からもバッテリーの状態を判断できることがあります。
例えば、充電器を接続しても充電を示すランプが点灯しない、あるいは点滅を続ける場合は、バッテリーの認識に問題が生じている可能性があります。また、充電開始直後に充電完了を示すランプが点灯する場合は、バッテリーが充電を受け付けない状態になっていることが考えられます。
さらに、一部のメーカーの充電器はエラーコードを表示する機能を持っており、ランプの点滅パターンによってバッテリーの異常を知らせます。取扱説明書を確認し、そのエラーコードが何を意味するのか確認することで、バッテリーの状態をより正確に把握できるでしょう。
これらのサインは単独で現れることもあれば、複数同時に現れることもあります。いずれにせよ、これらの症状が見られるようになったら、バッテリーの交換時期を検討するタイミングと言えるでしょう。
3. バッテリー寿命を延ばす7つの方法
電動アシスト自転車のバッテリーは決して安いものではありません。交換費用は2万円から5万円程度かかることが一般的です。そのため、できるだけバッテリーの寿命を延ばす工夫をすることで、経済的にもメリットがあります。ここでは、バッテリー寿命を延ばすための効果的な方法を5つの観点から詳しく解説します。
3-1. 正しい充電方法
バッテリーの寿命を延ばす上で最も重要なのが、適切な充電習慣です。リチウムイオンバッテリーは、満充電と完全放電を繰り返すよりも、30%〜80%程度の範囲内で使用する方が寿命は長くなります。
まず、毎回使用後に充電するという習慣は見直してみましょう。バッテリー残量が50%以上ある場合は、必ずしも充電する必要はありません。残量が30%程度になったタイミングで充電を始めるのが理想的です。
また、充電しっぱなしの状態も避けるべきです。多くの充電器には過充電防止機能が付いていますが、満充電状態が長時間続くことはバッテリーにとって負担となります。充電が完了したら、なるべく早く充電器から外すようにしましょう。バッテリーは満充電後もわずかに自然放電して電圧が下がっていきます。その状態で充電器がつながっていると、充電器が再び作動し、少量の充電を再開します。これが繰り返されると、小さな充放電サイクルが何度も発生することになり、バッテリーへの負荷が蓄積されます。よって、充電器を装着したまま、通電しっぱなしの状態で何日も放置することは避けましょう。
さらに、メーカー純正の充電器を使用することも重要です。互換性のない充電器を使用すると、電圧や電流が適切でなくバッテリーを傷める可能性があります。
長期間使用しない場合は、バッテリー残量を40%〜60%程度にしてから保管するのが最適です。完全に充電した状態や、逆に完全に放電した状態での長期保管は、バッテリーの劣化を早めます。
3-2. 適切な保管条件と環境
バッテリーの保管環境も寿命に大きく影響します。理想的な保管温度は10℃〜25℃程度の涼しい場所です。
夏場は特に注意が必要で、直射日光の当たる場所や車内など高温になる場所にバッテリーを置いたままにするのは避けましょう。40℃以上の環境では、バッテリー内部の化学反応が活発になりすぎて劣化が促進されます。
逆に、極端な低温環境も避けるべきです。冬場に屋外の物置などに保管すると、バッテリー内部の電解液が凍結するリスクがあります。凍結したバッテリーは内部構造が損傷し、最悪の場合は使用不能になることもあります。
また、湿度の高い場所での保管も避けましょう。バッテリーの端子部分が湿気にさらされると、酸化や腐食が進みやすくなります。バッテリーを取り外して保管する場合は、乾燥した場所に置き、端子部分にはカバーをするとより安心です。
長期間使用しない場合は、バッテリーを自転車から取り外して室内で保管することをお勧めします。3ヶ月以上使用しない場合は、その間も1〜2ヶ月(最長でも3か月)に一度、30分程度の充電を行うと自己放電による完全放電を防ぐことができます。
3-3. 過放電を避ける使い方
リチウムイオンバッテリーの大敵の一つが「過放電」です。バッテリー残量が完全にゼロになるまで使用すると、内部のセルが深刻なダメージを受ける可能性があります。
電動アシスト自転車の多くは、バッテリー残量が一定以下になるとアシスト機能が自動的に停止するように設計されていますが、それでもバッテリー表示が「残りわずか」になったら、できるだけ早く充電するようにしましょう。
特に、バッテリー残量が少ない状態で自転車を長期間放置すると、自己放電によって過放電状態になりやすくなります。1ヶ月以上使用しない場合は、ある程度充電してから保管するよう心がけましょう。
3-4. 定期的なメンテナンス
バッテリー自体にも定期的なメンテナンスが必要です。特に注意したいのがバッテリーの端子部分です。
端子部分は時間の経過とともに酸化したり、埃や汚れが付着したりします。これにより接触不良が起こると、充電効率の低下や走行中の電力供給不足につながります。定期的に、乾いた柔らかい布で端子部分を清掃しましょう。ひどい汚れの場合は、エタノールを少量含ませた布で拭き取り、その後完全に乾かすとより効果的です。
また、バッテリーマウント(自転車に取り付ける部分)も定期的に点検しましょう。バッテリーが確実に固定されていないと、走行中の振動でバッテリーと端子の間で瞬間的な接触不良が発生し、電力供給が不安定になったり、通信エラーが発生します。
3-5. 極端な気温での使用を避ける
バッテリーの性能は気温に大きく左右されます。特にリチウムイオンバッテリーは、極端な高温や低温での使用に弱い特性があります。
真夏の炎天下や、直射日光が強く当たる場所に長時間駐輪するのは避けましょう。バッテリーの温度が上昇すると内部抵抗が増加し、エネルギー効率が低下するだけでなく、化学反応が進みやすくなって劣化が早まります。
一方、冬季の氷点下の環境では、バッテリーの化学反応が鈍くなり、一時的に容量が低下します。これは直接的な寿命の短縮にはつながりませんが、バッテリー残量の急激な減少を招き、結果として過放電のリスクを高めます。
冬季に電動アシスト自転車を使用する場合は、可能であれば使用直前までバッテリーを室内で保管し、使用後も速やかに室内に持ち込むことをお勧めします。また、氷点下での使用後にすぐ充電するのではなく、バッテリーの温度が室温に戻ってから充電を開始するとより安全です。
バッテリーカバーや断熱材で保護することで、急激な温度変化からバッテリーを守ることもできます。特に冬季は、バッテリーを保温することで容量低下を最小限に抑えることができます。市販の専用カバーもありますので、寒冷地にお住まいの方は検討してみるとよいでしょう。
4. バッテリー交換について知っておくべきこと
いくら丁寧に扱っても、電動アシスト自転車のバッテリーにも寿命は訪れます。バッテリーの性能が明らかに低下したと感じたら、交換を検討する時期です。ここでは、バッテリー交換に関する重要な情報をご紹介します。
4-1. 交換時期の見極め方
バッテリー交換のタイミングは、使用状況や個人の優先事項によって異なります。しかし、一般的には次のような状況になったら交換を検討すべきでしょう。
まず、新品時と比較して走行距離が60%以下になった場合は交換時期と言えます。たとえば新品時に30kmの走行が可能だったバッテリーが、フル充電しても18km程度しか走れなくなった場合は、バッテリーの容量が大幅に低下している証拠です。
次に、充電に関する問題が頻発するようになった場合も交換を検討すべきです。充電器を接続しても充電されない、充電してもすぐに残量がゼロになる、あるいは充電中にバッテリーが異常に熱くなるといった症状は、バッテリーの内部に深刻な問題が発生している可能性があります。
また、バッテリーの外観に変化が見られる場合は安全のためにも直ちに交換すべきです。バッテリーケースの膨張、亀裂、液漏れなどは発火や爆発のリスクがあります。このような状態のバッテリーは使用を中止し、販売店に相談してください。
さらに、自転車の使用頻度や目的も交換時期の判断材料になります。通勤や業務で毎日長距離を走行する場合は、少しでも走行距離が低下したと感じたら早めに交換した方が効率的です。一方、週末の趣味程度の使用であれば、ある程度の性能低下は許容できるかもしれません。
4-2. メーカー純正品を選ぶ理由
電動アシスト自転車のバッテリー交換を検討する際、選択肢として「メーカー純正バッテリー」と「互換バッテリー」が存在します。しかし、安全性や信頼性を最優先するのであれば、メーカー純正品の使用が圧倒的に推奨されます。
● 純正バッテリーの信頼性と安心感
メーカー純正バッテリーは、自転車本体との適合性が前提として設計・製造されており、性能面でも安全面でも高い信頼性が保証されています。
また、製品にはメーカー保証が付いていることがほとんどで、不具合が発生した際にも安心してサポートを受けられるというメリットがあります。
● 互換バッテリーのリスク
互換バッテリーは価格が安いという点が注目されがちですが、品質には大きなばらつきがあり、過放電や発熱、発火など重大なトラブルにつながるケースや、自転車側のメーカー保証が無効になる場合もあります。
大前提として、日本国内で販売される電気製品には、電気用品安全法に基づく「PSEマーク」の表示が義務付けられています。これは、製品が法的に定められた安全基準をクリアしていることを示すものであり、PSEマークのないバッテリーは、そもそも日本国内での販売が違法である可能性もあります。信頼できる販売元の製品を選択する必要があり、万一の事故や故障を考えれば、信頼できる純正品を選ぶことが、結果的には安全でコストパフォーマンスにも優れた選択と言えるでしょう。
4-3. 古いバッテリーの処分方法
使用済みのバッテリーは家庭ごみとして捨てることはできません。リチウムイオンバッテリーには環境に有害な物質が含まれており、不適切な処理は環境汚染や火災の原因になります。正しい処分方法を知っておきましょう。
最も推奨される方法は、バッテリーを購入した自転車販売店やメーカーに引き取ってもらうことです。多くの販売店やメーカーでは、リサイクル処分の対応を行っています。場合によっては、引き取り料金が発生することもありますが、確実に適切な処理がされるため安心です。
自治体によっては、小型充電式電池のリサイクル回収を行っていることもありますが、電動アシスト自転車のバッテリーのような大型のものは対象外となっていることが多いため、事前に確認が必要です。また、家電量販店などに設置している「リサイクルボックス」でも、一部の小型充電式電池を回収していますが、電動アシスト自転車のバッテリーはサイズが大きすぎて対象外となっている場合もあります。
廃棄物処理業者に直接依頼する方法もありますが、費用がかかることと、適切に処理してくれる業者を見つける必要があります。いずれにしても、不法投棄は厳重に禁止されているため、必ず正規のルートで処分するようにしましょう。
バッテリーを処分する際には、端子部分をテープなどで絶縁し、ショートによる発火を防止することも重要です。また、バッテリーに残っている電気は可能な限り使い切っておくと安全です。ただし、完全に放電させることは避け、20〜30%程度の残量を残した状態で処分することが推奨されています。
5. まとめ
電動アシスト自転車のバッテリーは、適切な使用方法と管理によって寿命を最大限に延ばすことができます。本記事で解説した内容を簡潔にまとめると以下のようになります。
まず、電動アシスト自転車のバッテリー寿命は一般的に2〜5年程度、または充放電回数で500〜800回前後が目安です。ただし、使用頻度や使用環境、メンテナンス状況によって大きく異なります。バッテリー容量は経年劣化によって徐々に低下し、新品時の60〜70%まで低下した状態が実質的な「寿命」とされています。
バッテリーの寿命が近づいているかどうかは、走行距離の低下、充電時間の変化、アシスト力の弱まり、バッテリー本体の膨張や変形、充電器のランプ表示の異常といったサインから判断できます。特に、新品時と比較して走行距離が70%以下になった場合は交換時期が近いと考えられます。
バッテリー寿命を延ばすためには、以下の点に注意しましょう:
- 正しい充電方法:バッテリー残量が30%程度になったら充電を始め、満充電後は速やかに充電器から外す。
- 適切な保管条件:10〜25℃の涼しい場所で保管し、極端な高温・低温環境を避ける。
- 過放電を防ぐ:バッテリー残量がゼロになるまで使用せず、長期間使用しない場合は40〜60%程度充電しておく。
- 定期的なメンテナンス:バッテリー端子の清掃や、バッテリーマウントの点検を定期的に行う。
- 極端な気温での使用を避ける:特に高温環境下での使用と充電は劣化を早める。
バッテリー交換を検討する際は、メーカー純正品を選択するようにしましょう。メーカー純正品は高価ですが信頼性が高く、互換バッテリーは比較的安価ですが安全上のリスクがあります。バッテリーの購入先としては、自転車販売店、メーカー直販、家電量販店、オンラインショップなどの選択肢があります。
使用済みのバッテリーは必ず正規のルートで処分しましょう。家庭ごみとして捨てることは環境汚染や火災の原因になるため、絶対に避けてください。
電動アシスト自転車のバッテリーは決して安いものではありませんが、本記事で紹介した方法で適切に管理することで、長く快適に使用することができます。バッテリーが最大限の性能を発揮すれば、日々の移動がより快適になり、電動アシスト自転車の魅力をより長く楽しむことができるでしょう。
また、バッテリー技術は日々進化しており、今後はより長寿命で高性能なバッテリーが開発されることも期待されます。メーカーからの情報や、販売店からのアドバイスにも注目しておくと良いでしょう。最新の情報に基づいた適切なバッテリー管理を心がけることで、電動アシスト自転車との快適な生活を長く続けることができます。
よくある質問(Q&A)
Q1: 電動アシスト自転車のバッテリーを長持ちさせるためには、毎回使い切ってから充電した方が良いのでしょうか?
A1: いいえ、リチウムイオンバッテリーの場合は、完全に使い切ってから充電する必要はありません。むしろ、バッテリー残量が30%程度になったら充電を始め、満充電後は速やかに充電器から外すことをお勧めします。リチウムイオンバッテリーは、満充電と完全放電を繰り返すよりも、30%〜80%程度の範囲内で使用する方が寿命は長くなります。完全に放電させると内部のセルが深刻なダメージを受ける「過放電」状態になるリスクがあります。
Q2: 冬になると電動アシスト自転車のバッテリーの減りが早くなりますが、これは劣化しているのでしょうか?
A2: 冬季に走行距離が短くなるのは、必ずしもバッテリーの劣化が原因ではありません。リチウムイオンバッテリーは低温環境下で一時的に性能が低下する特性があり、特に0℃以下の環境では顕著です。これは化学反応が鈍くなることによるもので、気温が上がれば性能も回復します。ただし、極端な低温環境でのバッテリー使用は避け、可能であれば使用直前まで室内で保管し、使用後も速やかに室内に持ち込むことをお勧めします。また、氷点下での使用後にすぐ充電するのではなく、バッテリーの温度が室温に戻ってから充電を開始するとより安全です。
Q3: PSEマークって何?
A3: PSEとは、「Product Safety Electrical Appliance & Materials(電気用品安全法)」の略称で、日本国内で販売される電気製品に対して、一定の安全基準を満たしていることを示すマークです。電動アシスト自転車のバッテリーや充電器などは、感電や発火のリスクを伴うため、PSEマークの表示が法律で義務付けられています。このマークがない製品は、法的に販売できないだけでなく、安全性にも大きな不安があるため、使用は絶対に避けるべきです。
PSEマークは、以下のような2種類があります:
● ひし形マーク(特定電気用品):特に危険性の高い製品に対する厳しい審査基準
● 丸形マーク(その他の電気用品):一般的な電気製品向け
通常、電動アシスト自転車のバッテリーには丸型マーク。充電器にはひし形マークが該当します。